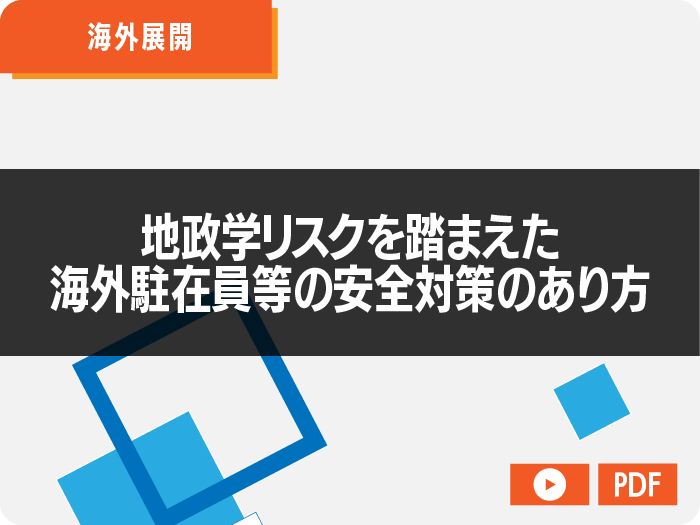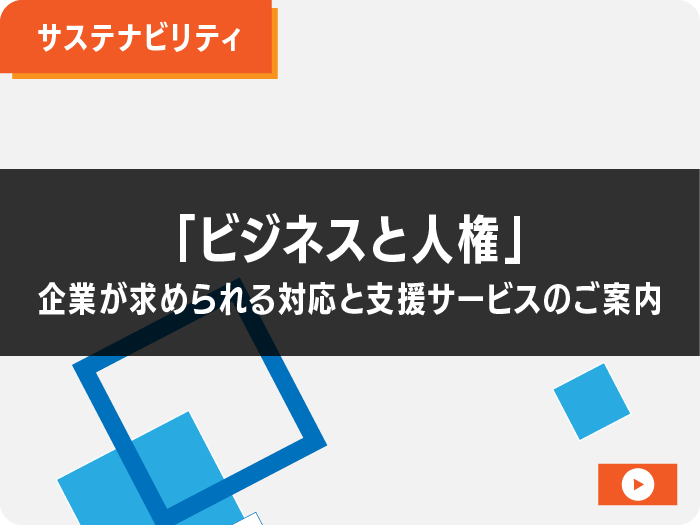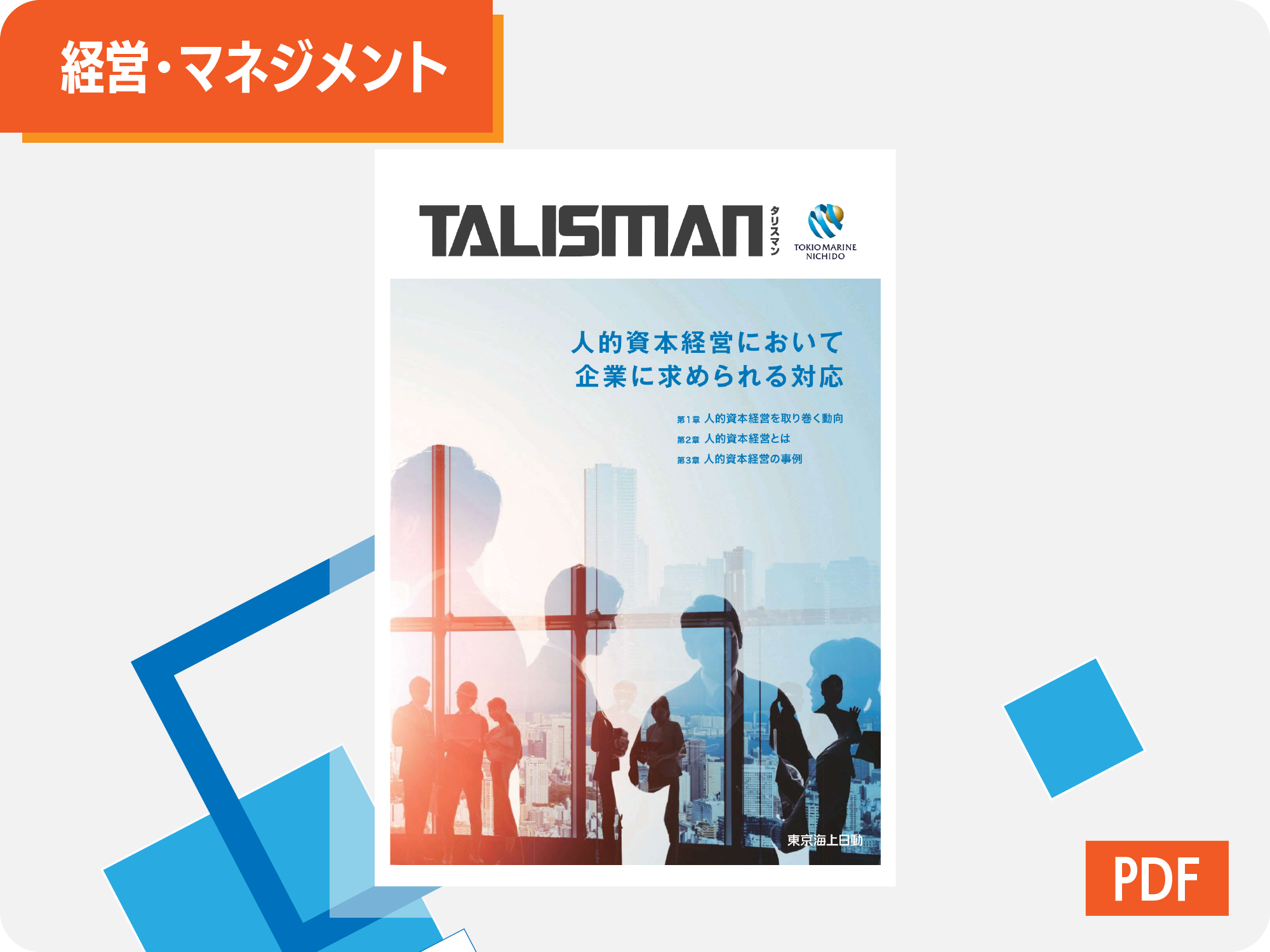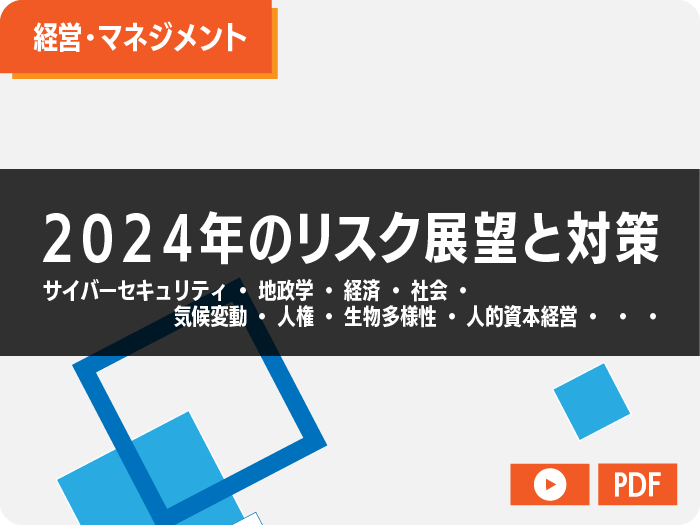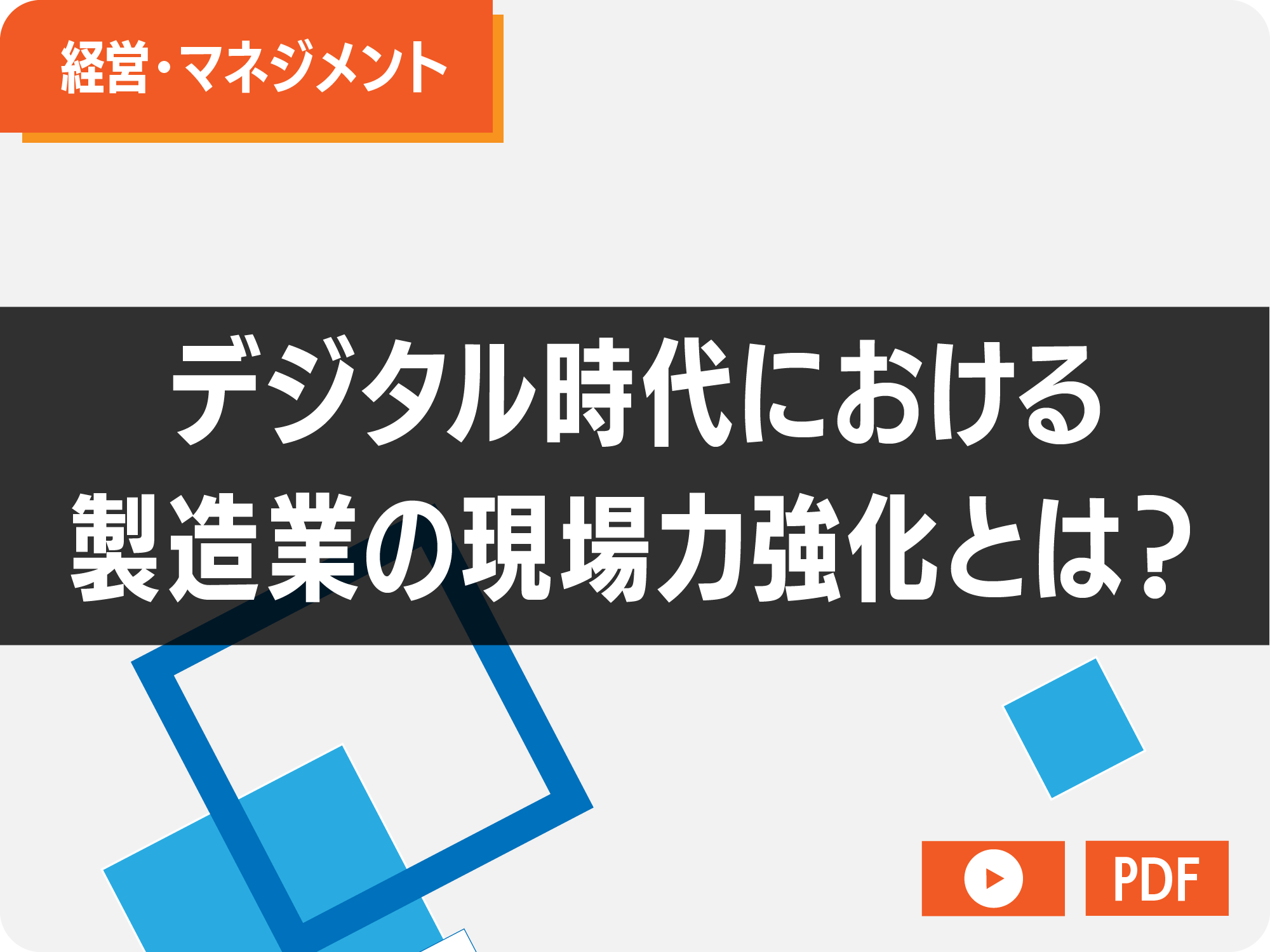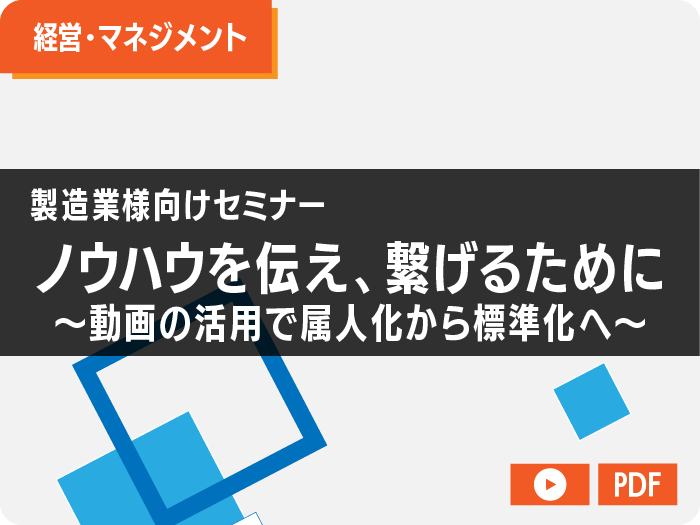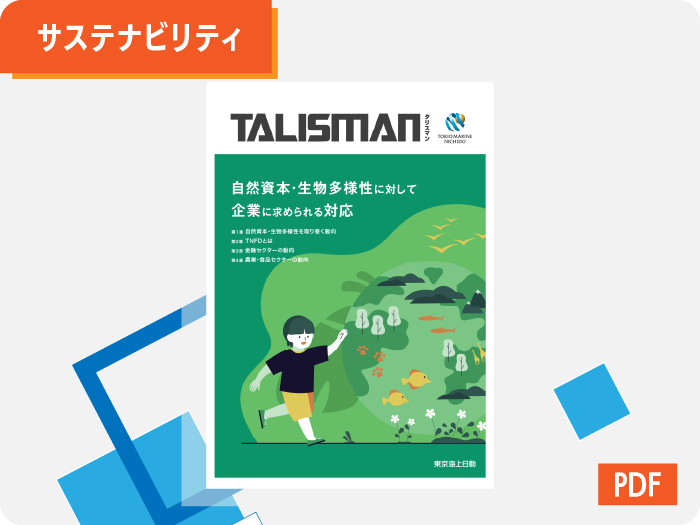Search products
Search results 11 cases
- Category: 経営・マネジメント
※本コンテンツは2025年5月に開催し、大好評をいただいたオンラインセミナーのアーカイブ配信です。
※本コンテンツでは第2部のみ配信いたします。
近年、戦争・紛争、デモ・暴動等の報道を目にすることが増えています。米中を軸とする地政学的分断の進展、長引くロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・パレスチナ戦争の影響等を背景に、先進国等これまで安定しているとみられてきた国・地域でも、大規模なデモ・暴動等が起きています。また日本企業の多くが進出する東アジアでは、台湾有事、朝鮮半島有事が引き続き懸念されています。
海外に駐在員や帯同家族、出張者を派遣する企業には、従業員の安全配慮義務の観点から、様々な安全対策と危機管理体制構築が求められ、加えて、刻々と変化する地政学リスクに対する理解が求められます。
本セミナーでは、東海大学平和戦略国際研究所所長・前ロシア連邦駐箚特命全権大使 上月豊久様から、ロシアの国内情勢と対外関係の見通しについてご解説いただいた後、弊社コンサルタントから、企業の海外安全対策・リスクマネジメントとして、具体的にどのような対策が求められるかを解説して参ります。
第2部
地政学リスクと企業における海外危機管理体制の構築
東京海上ディーアール株式会社
ビジネスリスク本部 上級主席研究員 深津 嘉成
AIの利活用を前提としてあらゆる事業・サービスが設計・運営される「AIファースト」の時代の到来により、企業はAI利活用に向けた取組を加速することが求められています。
一方で、AI技術の利用範囲及び利用者の拡大に伴い、AIの利活用による社会的インシデントも発生しています。AIにおいてはビジネスに創造性をもたらす反面、安心・安全に活用するためのガバナンスの構築が今まさに必要となっています。
本誌では、AIの利活用にチャレンジする企業の皆様が、AIガバナンスの取組を始められるように、実際のインシデントやリスクの事例を交えながらその要点を整理し、企業に求められるAIガバナンスについて解説します。
目次
はじめに
Ⅰ AI・生成AIに関する基本情報
1-1 人口知能とは何か
1-2 なぜAIが再び脚光を浴びているのか
1-3 AI・生成AIが人間にもたらすメリット
Ⅱ 業界ごとのAIインシデント
Ⅲ AIリスクの概説
3-1 AIの技術的リスク
3-2 AIの社会的リスク(倫理・コンプライアンス関連リスク)
3-3 その他AIリスクの包括的な特徴
3-4 (まとめ)AIリスクに向き合うためのポイント
Ⅳ リスク対応のためのAIガバナンス
4-1 AIガバナンスとは
4-2 アジャイル・ガバナンスの考え方
4-3 AIガバナンス構築の流れ
4-4 実効性のあるAIガバナンスにするポイント
4-5 AIガバナンスの根拠規程の整備
Ⅴ「AIガバナンス総合コンサルティングサービス」のご案内
おわりに
参考文献
(付録)AIインシデント事例集
小売
飲食・食品
運輸・物流
不動産
人事
法務
公共サービス
情報通信・メディア
保健衛生サービス
金融・保険
意図的な偽情報・誤情報の脅威
ヒューマンエラーによるインシデント
--------------------
発行:2025年2月
提供:東京海上日動火災保険株式会社
作成:東京海上ディーアール株式会社
目次
自然資本・生物多様性が危機的な状況にある今、自然資本や生物多様性の減少をプラスに回復させる「ネイチャーポジティブ」な社会への移行に向けて、企業に対しても生物多様性への影響を減らし、リスク低減に努め、その情報を開示することが求められています。
この自然資本・生物多様性に関するリスク管理体制の構築および情報開示に関するガイダンスの作成が、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)によって進められ、2023年9月には最終版が公表されました。
本誌では、これから自然資本・生物多様性への対応に取り組む企業の経営層・サステナビリティ関連部署に向けて、「なぜ取り組まなければならないか」「どのように取り組むか」「何を分析し、開示するか」について以下の構成で解説しています。
※本コンテンツは閲覧のみ可能です。印刷・ダウンロードはできません。
※冊子版をご希望の場合は、こちらからお申込みください
目次
Ⅰ 自然資本・生物多様性を取り巻く動向
1-1 国際的な動向
1-2 開示の動向
Ⅱ TNFDとは
2-1 設立背景
2-2 TNFDベータ版v0.4の構成と内容
Ⅲ 金融セクターの動向
3-1 UNEP FI TNFDパイロットプログラム
3-2 TNFDベータ版v0.4の追加ガイダンスにおけるリスク評価手法
3-3 BNPパリバ・アセットマネジメント社(BNP Paribas Asset Management)
Ⅳ 農業・食品セクターの動向
4-1 TNFDベータ版v0.4の追加ガイダンスにおける農業・食品セクター固有のコア指標
4-2 ケリング社(Kering)
4-3 キリン社(キリンホールディングス株式会社)
--------------------
発行:2023年9月
提供:東京海上日動火災保険株式会社
作成:東京海上ディーアール株式会社
本誌では、「ビジネスと人権」の取り組みを始める企業の担当者を読み手として、I~III章では「ビジネスと人権」に関する国内外の動向を解説しています。IV章では日本企業の取り組み状況およびインタビューを基にした企業の取組事例を紹介しており、すでに取り組みを始めた企業の方にもお読みいただける内容となっております。「ビジネスと人権」は、サステナビリティや経営企画、人事、調達、法務など社内の様々な部署も含めて全社的な対応が求められます。
※本コンテンツは閲覧のみ可能です。印刷・ダウンロードはできません。
※冊子版をご希望の場合は、こちらからお申込みください
目次
Ⅰ 「ビジネスと人権」に関する国際的な動向
1-1 企業に人権への取り組みを促す国際的な枠組み
1-2 「ビジネスと人権」に関する法制化の動向
Ⅱ ESG投資と「ビジネスと人権」
2-1 ESG投資の潮流
2-2 「ビジネスと人権」への取り組みに関する情報開示の動向
2-3 「ビジネスと人権」に関する外部評価
Ⅲ 日本における「ビジネスと人権」に関する動向
3-1 「ビジネスと人権」に関する行動計画
3-2 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
Ⅳ 日本企業の取り組みの現状
4-1 「ビジネスと人権」に係る日本企業の取り組みの傾向
4-2 「ビジネスと人権」に係る日本企業の取り組み事例紹介
企業事例 1 アサヒグループホールディングス株式会社
企業事例 2 日本郵船株式会社
企業事例 3 三菱地所株式会社
--------------------
発行:2023年2月
提供:東京海上日動火災保険株式会社
作成:東京海上ディーアール株式会社